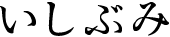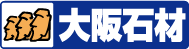手まり遊びで仏を語る~歌と書を愛した良寛さま
隆泉寺の良寛禅師墓。付近には自筆で「南無阿弥陀仏」と書かれた碑も立つ。
墓前の樹にズズメバチの巣があり、手に汗握る墓参だった
「この里に 手まりつきつつ 子どもらと 遊ぶ春日は 暮れずともよし」
(里で手まりをつきながら子どもらと遊ぶ春の一日が楽しく、このまま暮れずともかまわない)
心優しい歌人、書家として知られる江戸後期の禅僧・良寛は、1758年に新潟・出雲崎の名家に生まれた。父は地元の名主であったが、良寛は人の上に立つことを嫌い、家を継がずに17歳で出家する。
20代は岡山の高僧の元で修行に明け暮れ、32歳で悟りの証明書となる印可状を授けられた。翌年から諸国を托鉢行脚で巡り始め、40代になって故郷に戻る。
「草枕 夜ごとに変はる 宿りにも 結ぶは同じ ふるさとの夢」
良寛は出雲崎付近を無一文で転々と移り住んだ後、国上寺の五合庵で10数年を過ごし、54歳で代表作となる自選歌集・『布留散東』をまとめ、この頃から多くの名筆を残した。
ある日、良寛の草庵を訪れた長岡藩主・牧野忠精から「城下に招きたい」と直々に説得されたが、「焚くほどは 風がもて来る 落葉かな」(煮炊きに必要な落ち葉は風が運んでくれ、山里の暮らしに何の不足もない)の一句を無言で指し示し、要請を断ったという。
70歳を前に老いを感じた良寛は、30年過ごした国上山から下り、島崎村(長岡市)の知人宅に身を寄せて最後の5年間を送った。この地で28歳の若い尼僧・貞心尼が弟子入りし、40歳も年下の彼女に恋をした。
1831年、良寛は貞心尼に看取られ72歳で他界し、のちに彼女は良寛の和歌を集めた『蓮の露』を編集した。
良寛は出世欲と無縁で、生涯自分の寺を持たなかった。全ての人に愛情深く接し、庶民でも分かる平易な言葉を選んで仏教を広めた。そして、「子供の純真な心こそが仏の心」と悟り、懐には常に手毬を入れ、子供たちとよく遊んだ。かくれんぼで隠れたまま朝になったという逸話も残る。
「つきてみよ 一二三四五六七八 九の十 十をおさめて またはじまるを」
(一緒にまりをついてご覧。一二三四五六七八九十と、十が終わるとまた一から始まるね、これが仏の教えだよ)
生命を尊び、庵の下に生えてきた竹の子のために床に穴を開けたという。禅僧でありながら酒を好んだと伝えられ、親しみやすい良寛の姿が思い描かれる。
良寛の書は生前から奪い合いになるほど人気があり、人々が大切に保管したため約1,200首が残る。川端康成、水上勉など研究者は多い。
墓は晩年に世話になった木村家の菩提寺である隆泉寺(長岡市)に立ち、表面に次の歌が刻まれる。
「やまたづの 向かひの岡に 小牡鹿立てり かみなづき 時雨の雨に濡れつつ立てり」
(向かいの丘に雄鹿が立っている。10月の冷たい時雨に濡れながら凜と立っている)
建立時、孤独な鹿と良寛を重ねたのだろう。
辞世は「形見とて 何残すらむ 春は花 夏ほととぎす 秋はもみぢ葉」
(形見に何を残そうか。春は花、夏はほととぎす、秋は紅葉の葉っぱかな)
自然の恵みを感じる心を大切にして歌い続けて欲しいという、後世の私たちに向けたメッセージだ。
新潟県出雲崎の生家跡に建つ良寛像は、母の故郷・佐渡島を見つめている。
背後の良寛堂には良寛が昼寝で枕にした「枕地蔵」が収められている
※『月刊石材』2014年11月号より転載
| カジポン・マルコ・残月(ざんげつ) |